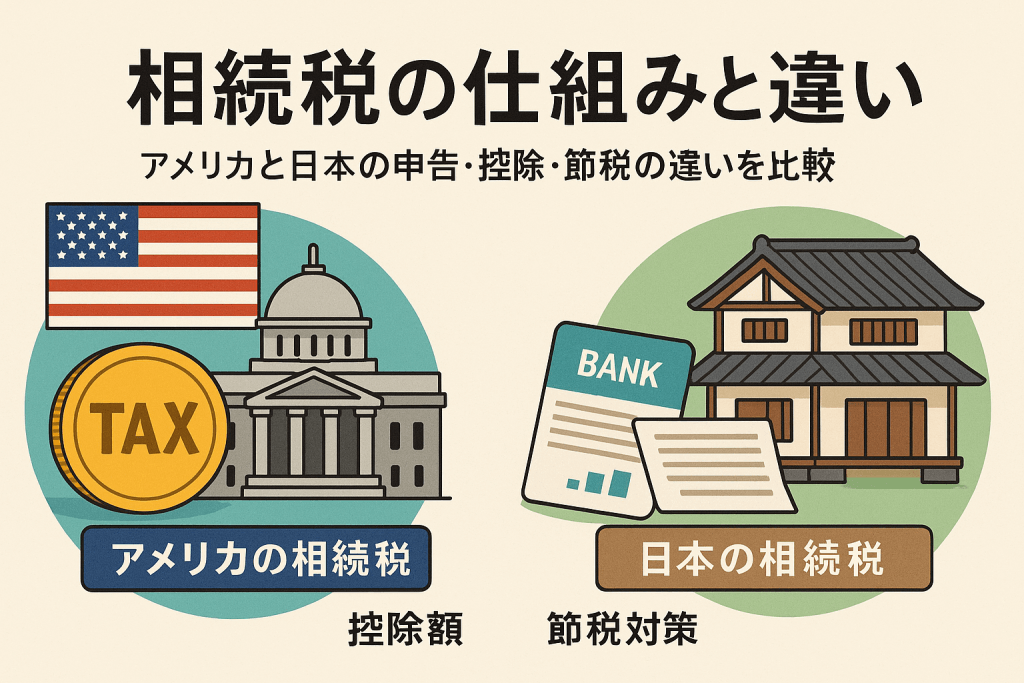「アメリカの相続税って、本当に一部の富裕層だけが対象なの?」
こう感じて調べ始める方は少なくありません。実際、米国の【2025年の連邦基礎控除額は約13,610,000ドル(日本円で約2億1,000万円)】と、日本の基礎控除額4,800万円と比べて圧倒的な差があります。大半の方はこのラインを超えることはないものの、州ごとに異なる遺産税や、日本と全く異なる納税義務など、「自分には関係ない」と思っている方ほど注意が必要です。
「非居住者やグリーンカード保有者、二重課税、プロベート手続き…正直どこまで理解すればいい?」
相続税を正しく把握しないと、思わぬ課税・手続き遅延など損失リスクが潜んでいます。また、2026年には基礎控除がさらに引き下げられる予定もあり、今後の資産計画には法改正情報の把握も不可欠です。
このページでは、アメリカ相続税の制度全体から【連邦・州別課税の実情】、国際相続で生じる複雑な課題まで、わかりやすく最新データとともに徹底解説します。
最後までお読みいただくことで、知らぬ間に損することなく、安心して相続・資産管理に臨める知識を手に入れてください。
アメリカの相続税とは|仕組みと日本相続税との根本的な違いを詳細解説
アメリカ遺産税と相続税の差異
アメリカでは「相続税」という名称よりも「遺産税(Estate Tax)」が一般的に使われています。この仕組みは日本の相続税と大きく異なり、課税のタイミングや対象となる主体が異なります。アメリカの遺産税は遺産全体に対して課税されるのに対し、日本の相続税は法定相続人ごとに財産の配分をもとに課税されます。
下記のテーブルで主な違いを整理します。
| 制度 | アメリカ(遺産税) | 日本(相続税) |
|---|---|---|
| 課税対象 | 被相続人の全遺産 | 相続人ごとの取得分 |
| 税の名称 | Estate Tax | 相続税 |
| 課税時点 | 被相続人死亡時 | 遺産分割の時点 |
| 基礎控除額(2025年例) | 約1,399万ドル(約21億円) | 3,000万円+600万円×相続人数 |
アメリカの遺産税は日本と比べて基礎控除額が高額で、課税対象はかなり限定される点も特徴として挙げられます。
アメリカ相続税の課税対象財産と相続人
アメリカの遺産税では、被相続人が死亡時に所有していた世界中の財産が課税対象になりますが、居住ステータスや国籍によって取扱いが異なります。「アメリカ市民」や「グリーンカード保持者」は全世界所得が対象になる一方、非居住外国人はアメリカ国内資産のみが課税対象です。
課税対象となる主な財産は下記の通りです。
-
不動産(アメリカ国内)
-
預金・金融資産
-
有価証券・株式等
-
生命保険(指定受取人がいない場合)
また、アメリカでは遺産税の納付責任は相続人ではなく故人の遺産財団(Estate)となります。日本のように各相続人が自分の取得分について申告納税する必要はありませんが、遺産全体の管理者や執行者には注意深い対応が求められます。
アメリカと日本の納税義務者と責任の違い
アメリカと日本の相続税における納税義務者の違いは制度の根幹に関わります。アメリカでは遺産税の納税義務者は「遺産財団(Estate)」そのものです。日本の場合、各相続人が自らの取得した財産に応じて申告・納税します。
リストで両国の責任範囲を比較します。
-
アメリカ
- 故人の財産全体に対して一括申告
- 納税義務は遺産財団(Estate)に発生
- 各相続人への分配前に納税完了が義務
-
日本
- 各相続人が自分の取得分について納税
- 配分後に個別申告・納税が必要
- 相続人ごとに税率・控除を適用
このように、アメリカの仕組みは納税手続きや責任の所在が明確で、遺産分配の前に税金の清算がなされる仕組みとなっています。相続の流れや最終的な負担者が異なるため、日米での二重課税や租税条約の活用など、国際相続を行う際は特に注意が必要です。
2025年のアメリカ相続税率・基礎控除額・いくらから課税かを徹底解説
連邦レベルの基礎控除額と税率詳細(18~40%)
アメリカの相続税は「遺産税」と呼ばれ、故人が残した遺産すべてに課税が行われます。2025年時点の連邦レベルでの基礎控除額は1,399万ドル(約21億円)と非常に高額です。この控除額を超える遺産に対し、18~40%の累進税率が適用されます。
下記のテーブルで主なポイントを整理します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 1,399万ドル(約21億円) |
| 課税方式 | 累進課税 |
| 税率 | 18%~40% |
| 適用対象 | 居住者(米国市民・グリーンカード保有者) |
| 控除超過分の課税 | 遺産全体で判定(相続人ごとでない点に注意) |
ポイント
-
米国市民やグリーンカード保有者が対象となります。
-
控除額以下の遺産であれば課税はありません。
州ごとの相続税・遺産税の違いと注意点
アメリカでは連邦遺産税に加えて一部の州でも独自の相続税や遺産税が課されます。州によって基礎控除額や税率が大きく異なるため、どの州に被相続人の財産があるかで実際の税負担が変わります。
下記の特徴があります。
-
州による差:主にメリーランド州やネブラスカ州などで州税あり
-
課税対象:州により相続人(受取人)や遺産そのものを対象とする
-
州独自の控除額・税率:たとえばオレゴン州は100万ドル超で1~16%の州税
| 州名 | 基礎控除額 | 税率範囲 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| メリーランド | 5万ドル | 0.8~16% | 相続税・遺産税双方存在 |
| ネブラスカ | 4万ドル(被相続人) | 1~18% | 受取人属性で税率変動 |
| ニュージャージー | 2万5000ドル~ | 11~16% | 2018年遺産税廃止後も一部課税あり |
注意点
-
州税の有無や控除額、税率は定期的に変更されます。
-
遺産の所在州を把握して早めに確認することが重要です。
2026年以降の基礎控除引き下げ予定とその影響
現行の1,399万ドルの基礎控除額は、2026年1月以降に約半額(700万ドル程度)へと大幅に縮小される予定です。これはトランプ減税(Tax Cuts and Jobs Act)の失効によるものです。控除額が下がることで、従来は非課税だった多くの資産家も課税対象になります。
影響について整理します。
-
基礎控除引き下げで課税対象者が大幅に増加
-
資産の生前贈与や信託活用による対策ニーズが高まる
-
日米両国で相続財産がある場合、二重課税への留意も必要
資産を米国に持つ場合は、専門家と相談し事前対策を立てることが不可欠です。特に日米両国で遺産や相続人がいる方は、租税条約や各国制度の詳細な確認をおすすめします。
相続税制度の変遷・トランプ政権の影響と廃止論議
歴代政権による遺産税変更履歴
アメリカの相続税(遺産税)は、歴史的に複数回の法改正を経て現在の制度が形作られています。直近100年の主な変更点として、20世紀初頭から相続税が恒常的に設けられ、各政権ごとに税率や基礎控除額が調整されてきました。
テーブルで主な改正履歴を整理します。
| 年代 | 主な内容 | 税率 | 基礎控除額 |
|---|---|---|---|
| 1970年代 | 高税率時代 | 最大77% | 約6万ドル前後 |
| 2001年 | ブッシュ減税施行 | 段階的に引下げ | 基礎控除引上げ |
| 2010年 | 一時的な廃止 | 廃止→35%復活 | 500万ドルへ拡大 |
| 2017年 | トランプ減税(TCJA)施行 | 最大40% | 約1,120万ドル以上へ急増 |
近年は基礎控除額の大幅な引き上げが特徴で、課税対象者の大幅な縮小につながっています。
トランプ政権下の減税政策とその法的影響
トランプ政権期の2017年には税制改革法(Tax Cuts and Jobs Act)が成立し、相続税の基礎控除額が大幅に拡大されました。これにより2025年までは個人で約1,220万ドル以上、夫婦合算で2,400万ドル超の遺産にのみ課税される水準となっています。
この改正で相続税を支払う対象者は全体の2%未満に激減しました。大部分の家庭が非課税となるため、「アメリカ 相続税 いくらから」「アメリカ 相続税 廃止」といった再検索ワードに見られるような、実際の課税対象や廃止動向への関心が急増しています。
ただし、このトランプ減税は一時的措置であり、2026年以降は基礎控除額が半減する可能性が濃厚です。今後の制度動向に注視が必要です。
世界の相続税ランキングにおけるアメリカの位置付け
アメリカの相続税制度は世界的に見ても特徴が際立っています。日本では基礎控除が低く、比較的多くの家庭が課税対象ですが、アメリカは高額の控除枠により実際の課税事例は限られます。
下記に主要国と比較した参考テーブルを掲載します。
| 国 | 最大税率 | 基礎控除額 | 日本円換算の目安 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 55% | 4,800万円 | 約3.2万ドル |
| アメリカ | 40% | 約1,220万ドル(2025年) | 約18億円 |
| ドイツ | 30% | 40万ユーロ(配偶者) | 約6,000万円 |
| 中国 | 0% | 制度なし | – |
アメリカは「相続税 ない国」ではありませんが、世界的には控除枠の大きさと課税対象の少なさで注目されています。廃止論議もたびたび起きますが、現時点では成立していません。各国の税制比較を理解し、自身の資産状況や国籍・居住地ごとの仕組みを正確に把握することが重要です。
非居住者・二重国籍者・グリーンカード所有者へのアメリカ相続税適用と注意点
非居住者の課税対象範囲と控除額の違い
アメリカでは、被相続人や相続人が非居住者の場合、相続税の課税対象となる資産範囲と控除額が大きく異なります。非居住者がアメリカ国内に不動産や株式などの資産を持っている場合、そのアメリカ国内資産が相続税の課税対象です。ただし、日本と比べて基礎控除額は大きく異なり、非居住者には基礎控除が6万ドル程度しか適用されません。これに対し、アメリカ市民や永住者(グリーンカード保有者)には1,399万ドル超(2025年時点)の大きな控除枠があります。
下記は対象者ごとのポイントです。
| 区分 | 課税対象範囲 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| アメリカ市民・永住者 | 全世界資産 | (例)1,399万ドル |
| 非居住外国人 | アメリカ国内資産のみ | 6万ドル程度 |
日本の相続税制度と大きな違いがあるため、海外資産の管理や申告には十分な注意が必要です。
二重国籍・グリーンカード保有者の国際相続上の留意点
二重国籍者やグリーンカード保有者の場合、アメリカの相続税は全世界の資産に対して課税される点が最大の特徴です。日本に居住している場合でも、アメリカ市民権やグリーンカードがあると、アメリカ国内外問わず全財産が課税対象となります。このため、日本とアメリカの両方で相続税の申告が必要となるケースが多くなり、いわゆる「二重課税」の問題が発生しやすいので注意が必要です。
主な注意点をまとめます。
-
全世界の資産が課税対象
-
相続財産が多額の場合、両国で申告義務が生じる
-
日米で手続きや評価基準が異なる
-
グリーンカード破棄後も一定期間は課税対象になる場合がある
相続順位や相続人の調査についても、日本の方式とは異なるため、専門家の助言が不可欠です。
日米間二重課税防止の租税条約活用法
日米相続税の課税権が重複する場合、日米租税条約を活用することで、二重課税の回避や軽減が可能です。この条約により、原則としてアメリカ国内資産はアメリカで、日本国内資産は日本で課税されます。さらに両国で納付した相続税のうち、一定額を控除できる相互控除の仕組みも設けられています。
主な活用ポイントは次の通りです。
-
アメリカ国内資産はアメリカ、その他の資産は日本で優先課税
-
控除や税額軽減の申請には複雑な手続きと書類準備が必要
-
租税条約の適用有無で納税額が大きく変わる場合がある
二重課税を防ぎ、適正な申告・納税とするためにも、早い段階で租税条約適用の可否を確認し、必要に応じて税務専門家に相談することが推奨されます。
アメリカ独特の「プロベート」制度|相続手続きの流れとリスク管理
プロベート制度の全体像と必要書類
アメリカの相続手続きで中心的な役割を持つのが「プロベート制度」です。プロベートとは、裁判所が遺言書の有効性を確認し、相続財産の分配・債務整理を監督する公的な手続きです。この制度は全米共通ですが、州によって運用や必要書類は異なります。
主なプロベート手続きの流れと必要書類は下記の通りです。
| 段階 | 主な内容 | 必要書類例 |
|---|---|---|
| 申立て | プロベート裁判所への申立て、遺言書提出 | 死亡証明書、遺言書、申立書 |
| 執行者の認定 | 執行者(Personal Representative)の選定・認定 | 執行者申請書、身分証明書 |
| 財産・債務調査 | 相続財産と債務のリストアップ、遺産目録作成 | 財産目録、債務一覧、各種明細書 |
| 債務・税金の支払い | 債権者への通知や税金(相続税・所得税等)の清算 | 税務申告書、支払証明書 |
| 相続財産の分配 | 残余財産の相続人への分配 | 分配明細、領収書 |
資料が揃わない場合や遺産に不動産が含まれる場合、手続きが長期化する傾向があります。プロベート申請前に必要な書類を確認し、漏れなく準備しましょう。
プロベートによる相続財産凍結のリスクとその対応
プロベート手続き中は、故人名義の財産(銀行口座・不動産など)が原則として「凍結」されます。すぐに遺族が自由に使えないだけでなく、債権者からの請求対応や税務処理が完了するまで分配が進みません。
このため、下記のようなリスクが発生します。
-
預金口座・証券口座が一時的に利用不可となる
-
不動産の売却や活用が制限される
-
手続き期間が数カ月から1年以上続く場合がある
-
債権者からの予期せぬ請求リスク
スムーズな対応のため以下の点が重要です。
-
必要書類や資産管理情報を事前に整理する
-
信頼できる執行者(遺言執行人)を指定する
-
債務状況や主要資産はリスト化し家族と共有しておく
また、プロベート費用は相続財産から差し引かれるため、遺族の生活資金に影響する場合もあります。事前準備と早めの情報共有がリスク軽減に役立ちます。
プロベート回避策としての信託や遺言書の活用法
アメリカではプロベートを回避または簡素化するために、信託(トラスト)や詳細な遺言書の活用が一般的です。下記に主な方法をまとめます。
| 方法 | 主なメリット | ポイント |
|---|---|---|
| 生前信託(リビングトラスト) | プロベート不要、資産分配がスムーズ、プライバシー保護 | 財産全体を信託化する |
| 共同所有(Joint Ownership) | プロベート回避、直接相続が可能 | 配偶者・親族と共有名義 |
| 指定受取人(Beneficiary Designation) | 生命保険・退職金口座などで活用 | 登録内容の定期見直し |
| 詳細な遺言書 | 意思を明確化し、分配トラブルを予防 | 専門家による作成推奨 |
特に信託の活用はプロベートを完全に避け、迅速な資産分配を実現できる点が大きなメリットです。また、遺言書を用いる場合も専門家に確認しておくことで、無効化や手続き遅延のリスクを減らせます。
これらの方法をうまく組み合わせることで、プロベートの負担軽減や相続税対策につながります。家族構成や資産状況に合わせ、最適な相続対策を早めに検討することが重要です。
生前贈与と節税対策|税制に基づく実務的対策パターン
生涯除外額(Unified Exclusion)の仕組みと活用方法
アメリカの相続税や贈与税では、生涯を通じて一定額まで非課税となる生涯除外額(Unified Exclusion)が設けられています。2025年は約1,399万ドルで、これを超える財産に相続税や贈与税が課されます。日本と比較すると、アメリカの基礎控除額は非常に高額です。
この制度の主なポイントは次の通りです。
-
年間贈与税控除(例:年間約1.8万ドル)は生涯除外額とは別枠
-
生涯除外額は生前贈与と相続財産の合算で利用
-
除外額を超えた場合、その分が累積課税対象
表:アメリカ・日本の基礎控除額比較
| 国名 | 基礎控除額 | 控除の性質 |
|---|---|---|
| アメリカ | 約1,399万ドル(2025年) | 生前贈与・相続共通 |
| 日本 | 3,000万円+600万円×法定相続人 | 相続時のみ |
年単位の贈与と組み合わせながら、生涯除外枠を余すことなく使うのが資産移転の最適解です。
信託設定や遺言書作成による資産移転最適化
多額の財産を次世代へスムーズに移すには、信託や遺言書の適切な活用が不可欠です。アメリカの信託制度を活かすことで、資産分配の柔軟性やプライバシー確保、州ごとのプロベート(遺産検認)回避といった効果が期待できます。
資産移転最適化の手法として
-
生前信託(Living Trust)の活用
-
納税負担の平準化(分割贈与・引受先を複数設定するなど)
-
明確な遺言書作成による紛争リスクの低減
が挙げられます。特に遺言書は英語・日本語両方で作成し、州ごとの相続規定や遺留分にも配慮しましょう。
信託や遺言書を専門家とともに設計することで、課税リスクや将来の争いを事前に回避できます。
税制改正リスクと失敗事例の回避方法
アメリカの相続税制は時の政権や法改正の動向に大きく左右されるため、常に最新情報をチェックし対策を早めることが重要です。例えば、トランプ減税政策による大幅な基礎控除額の引き上げは2025年に終了予定です。今後生涯除外額が半減するリスクも想定されます。
対策失敗の代表例は
-
制度変更前に贈与や信託を実行しなかった
-
州独自の遺産税を見落とした
-
非居住者や外国人への相続ルールを誤解した
などです。
回避策として
- 年ごとに最新の基礎控除額・税率を確認
- 州ごとの独自制度や課税対象を専門家と確認
- 国際相続時は日本との制度や条約も考慮
といった手順を徹底しましょう。失敗事例を回避し、最適な資産移転を実現するには早めの対策と定期的な見直しが不可欠です。
ケース別の実務対応|申告・納付フローと必要書類の具体的手引き
日本居住者が米国資産を相続した場合の申告フロー
日本居住者がアメリカ国内にある資産を相続する際、申告手続きは複雑です。まず、アメリカ連邦遺産税の申告を行う必要があります。申告の際には、連邦および州の基礎控除額と課税対象額を正確に理解し、期限内に書類を提出しなければなりません。特に2025年の基礎控除額や税率など、法改正の動向にも注意が必要です。申告プロセスは、おおまかに以下の流れで進みます。
- アメリカの弁護士や会計士に相談
- 相続資産の評価・証明
- 必要書類の収集(死亡証明書、不動産権利書など)
- 連邦遺産税申告書(Form 706など)の提出
- 納税と現地プロベート手続き
海外資産については日本でも申告が必要なため、二重課税を回避するため以上の点を早めに把握し、国際相続に精通した専門家のサポートを受けましょう。
申告トラブル回避のためのチェックポイント
アメリカの相続税申告でトラブルを回避するには、次のポイントを押さえることが重要です。
-
州ごとの相続税の有無と税率を必ずリサーチする
-
日米租税条約による二重課税防止措置の適用確認
-
期限内の申告・納付(通常は被相続人死亡後9か月以内、一部延長可能)
-
資産評価時の為替レート・評価基準の整合性
-
必要書類の抜け漏れや誤記載の防止
-
名義変更手続き、遺言執行者の選定可否にも注意
特にグリーンカード所有歴や、被相続人と相続人の居住状況によっても税制が異なるため、事前の調査が不可欠です。プロベート制度による相続財産の公開も加味しつつ、迅速な対応でトラブル回避を目指してください。
公的データ・最新申告フォームの入手方法と活用法
アメリカの相続税関連手続きを円滑に進めるには、公式データと最新の申告フォームを正しく利用する必要があります。主に利用されるのはIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)の公式サイトからの資料取得です。以下のテーブルに、代表的な公式資料とその利用目的を示します。
| 資料名 | 利用目的 | 入手先 |
|---|---|---|
| Form 706 | 連邦遺産税の申告 | IRS公式サイト |
| 州別のTax Forms | 州ごとの申告書類 | 各州政府ウェブサイト |
| IRS Publication 559 | 相続税の実務ガイド | IRS公式サイト |
| 最新基礎控除・税率表 | 税率・控除額の確認 | IRS、主要会計事務所公開サイト |
これらのフォームやデータを活用し、正確な申告・納付を心がけることで、後日の追加納税やペナルティリスクを減らすことが可能です。原本を英語で提出する場合、日本語訳の添付も重要となるため、専門家に確認しながら作業を進めてください。
よくある質問と誤解解消|アメリカ相続税の疑問を正しく理解するために
廃止されるという噂と真実
アメリカの相続税が「廃止された」という噂がときおり見受けられますが、現実には連邦遺産税は引き続き存在しています。2025年時点で連邦の基礎控除額(課税免除額)は約1,399万ドルで、一般的には高額な遺産に限定して課税されます。一部の州では独自の遺産税や相続税が課せられており、「廃止=全国で無税」という認識は誤りです。特に法改正やトランプ減税により基礎控除額が大幅に引き上げられた過去もありますが、今後は基礎控除額引き下げの議論も継続しており、税制動向を把握しておくことが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連邦遺産税 | 継続中 |
| 基礎控除額 | 約1,399万ドル(2025年時点) |
| 州独自の相続税 | 一部州で実施 |
| 廃止の可能性 | 現在は存在せず、今後も動向に注意 |
日本との二重課税が起きるかどうかの解説
日米双方に遺産や相続人が関わる場合「二重課税」が心配されますが、日米租税条約により双方で相続税を課せられる場合には、外国税額控除などで過大な納税が発生しないよう調整されています。しかし、遺産の内容や相続人の居住地、被相続人の国籍・居住歴などによって適用範囲や必要書類は異なります。専門家への事前相談がおすすめです。
-
二重課税対策の主な例
- 日本・アメリカ両方で課税対象の場合は控除制度を利用
- 非居住者やグリーンカード保有者の場合も要確認
- 資産所在地や居住ステータスの違いに注意
プロベートと遺留分の関係性
アメリカの相続手続きにはプロベート(遺言検認・裁判所管理)のプロセスがあり、これは遺言の有効性や遺産分割の公正さを確保する役割を担います。日本の「遺留分」(法定相続人に必ず残すべき財産割合)は州ごとに取り扱いが異なり、多くの州では日本のような必須制度がありません。そのため、遺言作成時や相続人の配分には慎重さが求められます。
| 比較項目 | アメリカ | 日本 |
|---|---|---|
| プロベート | 義務的、裁判所を通す | 必要な場合のみ |
| 遺留分 | 原則なし(州により一部あり) | 法定相続人に保障 |
生前贈与が相続税に与える影響
アメリカでは生前贈与税と相続税の基礎控除枠が共通で使われています。被相続人が生前贈与を行った場合、その合計額が基礎控除額から差し引かれ、残額を超えると贈与税や遺産税の対象となります。基礎控除額以内であれば非課税なので、贈与のタイミングや総額の計画が重要です。また、日本と異なり年間で一定額まで非課税となる「年間控除」も累積管理されるため注意してください。
-
生前贈与のポイント
- 贈与分も相続税の基礎控除枠内に含まれる
- 基礎控除額を超過すると税負担発生
- 年ごとの非課税枠も活用可能
グリーンカード所持者の税務申告義務
アメリカのグリーンカード(永住権)保有者は、居住地に関係なくアメリカの税法上「アメリカ居住者」として扱われます。そのため、全世界の資産が遺産税や贈与税の対象となる点は特に注意が必要です。日本に居住していてもグリーンカードを保持していればアメリカでの申告義務が生じるため、相続発生時は速やかな税務申告やプロベート手続きが求められます。
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 居住地要件 | グリーンカード保有者は居住地問わず納税義務 |
| 世界資産への課税 | 日本資産も課税対象となる可能性あり |
| 申告手続き | 税務署・裁判所への手続き、日米双方での対応が必要 |